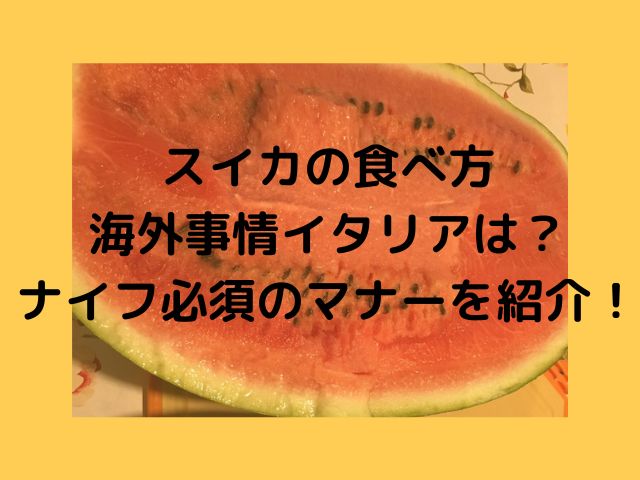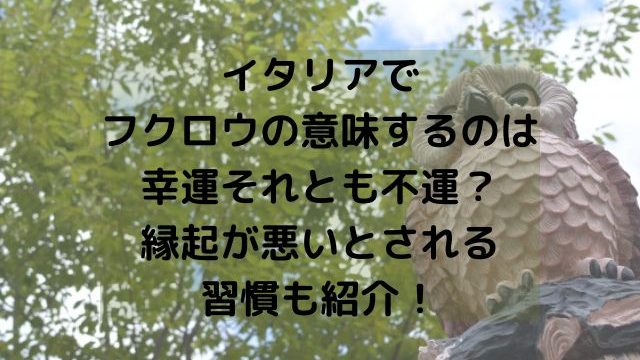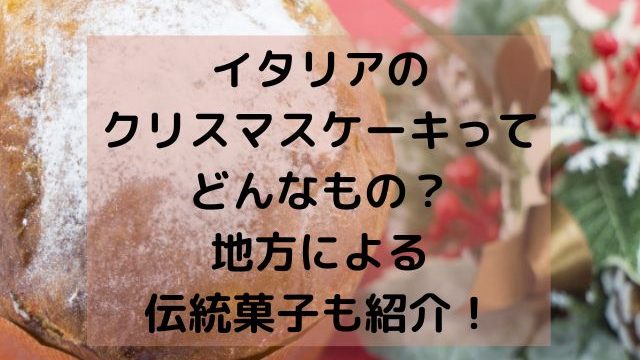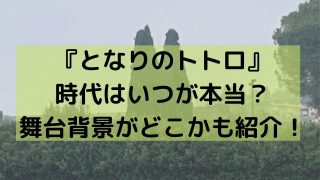今頃になってではありますが、今回はスイカの食べ方海外事情イタリアは?ナイフ必須のマナーを紹介!というテーマでお送りします。
夏といえばスイカ!
今年の夏は特に日本もヨーロッパも酷暑と言われていました。
我が家ではスイカは丸ごと購入が基本。
それが一個20キロ近くあったりするものだったりするので、その為にスイカを丸ごと入れる用の冷蔵庫があるくらいです。
畑を所有して家庭栽培でスイカを作っていた事もありました(笑)。
今年も沢山お世話になったスイカですが、日本と切り方や食べ方の常識としてのマナーがちょっと違う・・という事で、今年はもう晩夏ではありますが紹介しますね。
では、スイカの食べ方海外事情イタリアは?ナイフ必須のマナーを紹介!
お付き合いください!
目次
スイカの食べ方海外事情イタリアは?

イタリアでのスイカ事情
まず最初に、イタリアのスイカには日本のような丸いスイカや小玉スイカもありますが、一般的なのは長細い楕円形の形のスイカです。
しかも、日本だとスイカは緑に黒と言う印象ですが、イタリアだと緑に白い線ですね。
やはりスイカの産地として有名なところもあり、とっても甘いスイカもあればハズレのスイカもあります。
イタリアは野菜や果物は大概1キロあたり幾らと価格設定がされていますが、最初の頃の出始めは1キロあたり€1以上(現在は€1=約138円かなり円安です)から始まり、最盛期には売り出しで1キロあたり€0,50位になったりします。
切り売りだと少し割高になりますが、家族の場合は丸ごと買う人が多いです。
今年市場の大きかったスイカは22キロありました!
ハズレだったら泣きます。
我が家の家族はみんなスイカ好きなので、夏はスイカを切らす事はありません。
冷蔵庫にスイカスペースは必須なのです(笑)。
我が家の日常のスイカの切り方
I did not know yellow watermelon was a thing until now. Pretty sure we’re living in a simulation pic.twitter.com/Az5rEG6WR0
— Today Years Old (@todayyearsoldig) August 20, 2022
ある日、イタリア人の夫が『スイカの賢い切り方を学んだ!』と嬉しそうに言い、冷蔵庫で冷やしてあったスイカを切り始めました。
どう言う切り方かというと次の様なものです。
- 丸いスイカ(イタリアの場合は楕円形が多いですが)のヘタのあった頭の部分と反対側のお尻の方を最初に切り落とします。
- それから包丁を入れるとコロコロ転がることがないので安定してスイカを切り分けることができると言うものです。
ほんのちょっとの工夫なのですが確かに安定は大事ですね。
因みにTwitterで見つけた映像は中が黄色のスイカである事と、切り落としを片側しかしていないのでちょっと違うのですが、似ていたので採用させていただいました!
スイカを日頃手頃に食べられる用に

私はスイカの果汁でテーブルや床が汚れることを避ける為に、最初に半分の大きさ分はサイコロ型に切り分けてタッパーにしまうようにしています。
その際に少し手間でも出来るだけ種を取り除いてしまう事で、いっぺんに生ゴミの処理もできるし、食べる時にも種があまり気にならないですみます。
問題は、食べ易いのも手伝って我が家のスイカ消費量は半端なく多く、しかも早いので、手間をかけてもあっという間に容器が空っぽ!となっている事ですね。
スイカがあまり甘くなかった時は?
この様に種を取り除いてサイコロ状にしてあると、万が一スイカがハズレだった時にそのまま冷凍庫へ冷凍できます。
そして、凍らした後でミキサーにお砂糖とあれば牛乳少々、なければ水を足して撹拌すると美味しいスイカアイス(シャーベット)になります。
先ほど登場した長男のお友達が特に気に入ってくれて、我が家に来る度にスイカのアイス!とリクエストされていました(笑)。
夏の日本の風物詩スイカ割りは日本特有
先日道端に落ちて割れているスイカを見かけました。
どうやら買い物の帰りに気の毒なことに落として割ってしまった様です。
(そのまま放置してあると言うのもイタリアなのですがxxx)
ふと夏の日本の風物詩のスイカ割りを頭に浮かべたのですが、イタリアではそういう遊びは聞いた事ありません。
幾ら日本で庶民的な果物とされていても、日本でも丸ごと購入しようと思ったら結構高価ですよね?
昭和の時代にはそれほどでも無かったのでしょうか。
叩いて割ったら無駄になる部分が出てきますから、倹約主婦には嬉しくない行事ですが当時は楽しみでした!
調べてみたら、その起源は諸説があると言われるものの、その一つとして三国時代に遡るとありました。
内容はなかなか怖いものです(驚)。
以下引用文を紹介します。
スイカ割りが誕生した詳細な時期については、定かではないとのことですが、一説によれば、「三国志」の時代にはすでに行われていたと言います。なんでも、中国における戦の前の通例として、罪人を頭だけ出して砂に埋め、棍棒で叩くという儀式が行われていたとのこと。残虐さを見せつけることにより、相手側の戦意を喪失させるという狙いがあったのだとか。これにストップをかけたと言われているのが、あの諸葛孔明。残虐な様子を見かねた孔明の発案によって、頭がスイカに置き換えられるようになったそうです。その後には、海の神様へのお祈りとして、この儀式が日本に伝承され、現在のスイカ割りが生まれた……というのは、あくまでも諸説ある起源のうちの一つ。-Citrusより
スイカを食べる時にナイフ必須のマナーを紹介!

小学生だった頃の長男のお友達から気付かされたイタリアのマナー
長男がまだ小学校の頃の話です。
我が家によく遊びに来て食事を一緒にするお友達の中の一人に、スイカを振る舞った時にナイフを出さずにいたところナイフが欲しいと言われました。
「え?スイカはかじるものでしょう!?」
と半分驚いて言ったら(男の子だし!)、
「行儀が悪いとマンマ(母親)に怒られる!」と言われて少し恥ずかしい気分になった事があります。
しかもこのお友達のマンマは私よりも一回り以上も若いお母さんです(汗)。
その時まで全く気にせず、息子たちにも日本式で切ってスイカは齧って食べるもの!としていたのでハッと気付かされました。
言い訳ですが、当時夫は仕事でほとんど家にいなかったですし。
以来、スイカを食べる度にその時の事を思い出してナイフを必ず添える様にしています(笑)。
フォークは食事の時は添えてあったりしますが、無くても良くて重要なのはナイフです。
今では既に成人している長男の友達は、もはやそんな事は忘れているでしょうけれど。
夏のイタリアではスイカを切って売っている屋台があったりするのですが、使い捨ての容器に入れられたスイカにさえも使い捨てのナイフがついて来ます。
元々食事のマナーでもかじり付くことは良しとされていません。
パンも一口大にちぎって口に。
なので、基本はナイフで一口大に切ってから、と言うものです。
種も直接噴き出すのではなく、手にとってお皿に置くと言う感じですね。
切ってテーブルに置く時の切り方は、日本のように最初に横半分に切るのではなく縦(スイカの模様に合わせる様に)に切るのが基本です。
勿論とりわけ易い大きさに切り分けます。
対照的な日本の昭和・子供時代の思い出
私の場合、とてもありがたい事に田舎の祖父母が畑でスイカを始め色々な野菜や果物を作っていました。
夏休みは田舎で過ごす事が多かったので、軽トラックの荷台に乗せてもらって収穫にお供していました。
そしてそのスイカを、従姉妹たちと縁側に並んでかじり付いては種を吹き飛ばし競争をしていたと言う、昭和の子供時代を懐かしく思い出します(笑)。
多分昔からあるそんな日本の夏のイメージが、メロンが高級とされるのに対してスイカは庶民的とされる要因の一つかも知れませんね。
ワイルドな日本の伝統(?)の食べ方に比べてイタリアは上品に。
あ、因みにスイカに塩をふりかけるのはかなりイタリアでは驚かれます!
でも、メロンを生ハムと食べたりする国なのだから、似た様なものだと思うのですけれどね。
スイカの食べ方海外事情イタリアは?ナイフ必須のマナーを紹介!のまとめ

今回はスイカの食べ方海外事情イタリアは?ナイフ必須のマナーを紹介!というテーマでお届けしました。
何においても国によって違うものですね。
もう少ししたら、また自由に海外旅行を楽しめる様になるかなと願う日々ですが、イタリアで(恐らく他のヨーロッパの国でも)レストランでいきなりスイカにかぶりつくとびっくりされる可能性大です、
その様な事が起こらないように、頭の片隅に覚えておいていただければと思います。
日本の諺では『旅の恥はかき捨て』と言ったりもしますが、『郷にいれば郷に従え』という諺もあります。
マナーを心得ておいて損はないでしょう。
美味しくスイカを楽しみましょう!
最後までお付き合いありがとうございました!